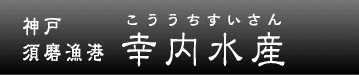 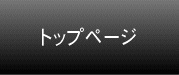 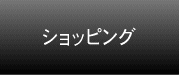 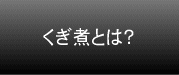 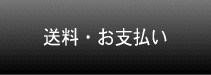   |
 いかなごのくぎ煮とは? いかなごのくぎ煮とは「いかなご」という魚の稚魚を佃煮にしたものです。 「くぎ煮」の誕生や名前の由来は数多く伝えられております。 「できあがりが錆びた釘のようだ」とか実際に釘を入れて炊いていたなど。 現在伝えられているくぎ煮に関する説をいくつかご紹介します。  漁師のまかない料理? 古くは長田港(神戸市長田区)の網元が自分達の獲ってきたいかなごを醤油と砂糖で煮て 自分たちの従業員に食べさせたのが始まりとされています。当時、砂糖は高級品であり、 一般では料理に使える家庭は少なかった。網元は他府県から来た従業員の食事を用意しなければならず、 元手がかからず保存性の高い料理ということで、いかなごを佃煮に加工しました。 網元は十分な財力により、砂糖を使うことができました。 戦後、砂糖や醤油が一般家庭に普及すると共に近隣の各家庭にくぎ煮は広まっていきました。 ガラス屋の副業? 上記の同じ頃、垂水のガラス屋は仕事が少なく、自店の強力な火力を利用していかなごを醤油と 砂糖で煮たことが垂水でのくぎ煮の始まりという説もある。 クギを煎ってるのか? くぎ煮という名前はもともと「釘煎り」という名前だったという説があります。 垂水の組合長が鍋返しをする姿を見て「釘でも煎ってるのか?」と聞いたのが始まりとされた 「釘煎り」→「釘り」→「釘煮」→「くぎ煮」という説。 いかなごの佃煮が、大工が家などを解体した際に出る古クギとよく似ていたため、 「くぎ似」→「くぎ煮」となった説もあります。 関西では2月後半の時期になるとテレビなどのマスメディアで 「瀬戸内海でいかなご漁が解禁になりました」と報道され、 阪神間の各家庭で春を告げる味としてくぎ煮が一斉に作られます。 人と人とが繋がり、感謝の気持ちとして全国に広がったというエピソード。 1995年に起こった阪神大震災でボランティアの皆様に御礼として全国に届けられ、 阪神間だけではなく日本中に知られるようになりました。 くぎ煮に関する 過去 現在 未来 いかなごのくぎ煮の起源について、様々な説が今も伝えられています。 「これが事実」と断定できるものは過去に戻って検証しない限りわからないのかもしれません。 これから先、現在のくぎ煮を知る私達が出来ることは「いかなごのくぎ煮」というものが、 どのように製造され、どのようなものが「いかなごのくぎ煮である」ということを 正しく伝えていかなければいけません。 そして本当の「いかなごのくぎ煮」を全国の皆様に神戸の郷土料理を 知ってもらえるよう努力しなければいけないと思います。  いかなごのくぎ煮のタレ くぎ煮のタレの調合に関して、醤油、砂糖(キザラ)、生姜と使用するのが基本形とされています。 ただ、この基本形ではツヤが出ず、いかなごが硬くなっていき、鍋からあげる適切な瞬間(約10~15秒)を 的確に見極めなければいけません。 素人にはこの技術は難しく、現在では各家庭で炊けるように研究が進られました。 そして各家庭お好みにより以下の調味料を加えくぎ煮へと加工されています。 酒:柔らかさを出す 水あめ:飴のコーティングにより保存性を高める みりん:硬くならずにテリを出す 現在神戸市漁協では醤油、砂糖(キザラ)、生姜の基本形にみりんを加えた味付けを推奨しています。 当店では水あめを使用し、くぎ煮に加工しています。  くぎ煮に最適ないかなごとは? くぎ煮に加工する際に一番味を左右するのは「鮮度」です。 小さい魚ゆえに鮮度の低下が早く、時間がかかるごとにいかなご本来のコシが失われていきます。 鮮度の良いいかなごをくぎ煮に加工するとグニャグニャと折れ曲がります。 阪神間のいかなごがくぎ煮に最適とされるのは水揚げから市場へ、 そして各家庭へと供給されるスピード(流通の経路)が確立されているからです。 朝のいかなご→餌を食べておらず、腹が裂けずくぎ煮に最適とされています。 昼のいかなご→餌を食べて腹の部分が赤く色づいている。腹が裂けやすくくぎ煮に加工するには難しいのですが いかなごの釜揚げに最適とされています。 水揚げの時間だけではなく、いかなご自体の大きさもくぎ煮の味を大きく左右します。 大きく育ったいかなごをくぎ煮に使用するとどうなるのか? 大きく育ったいかなごは脂がのり、くぎ煮にすると脂分が酸化しやすく黄色い色に変化しやすいです。 小さいいかなごは食感がやわらかく、お子様でもお年寄りの方でも食べやすいものです。 少し大きくなると魚自体に脂が出てくるので、こちらも魚本来の旨味が味わえます。 阪神間のご家庭では、お好みによりいかなごの大きさを見計らってくぎ煮に加工されています。  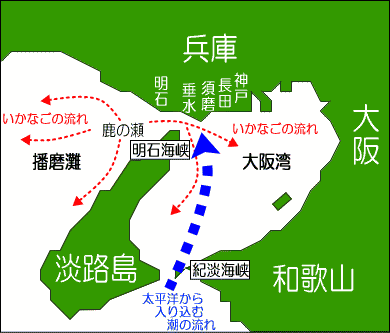 大阪湾から播磨灘はいかなごの生息に最適な環境 明石沖、淡路北部より西に位置する場所に砂地で比較的水深の浅い場所があります。 そこは鹿の背中の模様に似ていることから「鹿の瀬」と呼ばれています。 鹿の瀬は潮の流れが程よく、酸素の多い良質の海水が流れ込みます。 いかなごは越冬ならぬ越夏をします。 砂にもぐり冬の時期まで過ごすため生育条件の揃った鹿の瀬は生息するのに最適な場所となっています。 また、大阪湾は内湾と外洋の潮が入ってくるのため、海水中の栄養価が高く、魚の成長が早くなります。 紀淡海峡から流れ込む外洋の潮はちょうど須磨から垂水に当たるので、 この地域ではさらに栄養価が高い海水が流れ込むと考えられ、サンゴなどの生物も確認されています。 栄養分の多い水→魚の成長促進→軟骨が大きくなる→軟骨が旨味と柔らかい食感を生み出す。 いかなごの旨味は軟骨の成長具合によっても変化します。 ※以上の情報は神戸市漁協関係者、漁業関係者よりご提供頂いた情報を確認し掲載させて頂いております 情報をご提供下さいました皆様、心より感謝いたします 神戸市漁業協同組合 神戸市の西の端に位置し、明石海峡大橋を望む舞子地区(垂水区)から駒ヶ林地区(長田区)までの 大阪湾に面した地区で、昭和34年市内にあった7つの漁協が合併し、できた漁業組合です。  兵庫県立農林水産技術総合センター水産センター 水産資源の持続的利用と安全・安心な水産物の安定供給を図るため、 水産技術センターでは科学的調査研究と技術開発を実施し、その成果を行政機関、関係団体との 一体的な活動を通じて漁業者・県民に普及する他、行政施策の実施に役立てています。 |
幸内水産 〒654-0039 兵庫県神戸市須磨区鷹取町3-1-17 Tel/FAX 078-737-2539 ※日中のお問い合わせは加工作業のためお電話に出れない場合がございます。 お急ぎの時は 080-5335-4116(コウウチ)までご連絡ください。 |
| Copyright (C) 2006 幸内水産 All Rights Reserved |